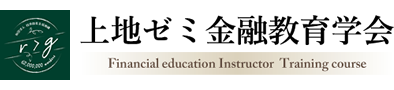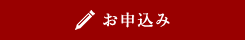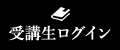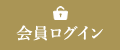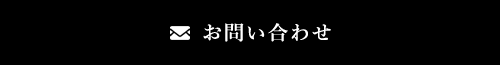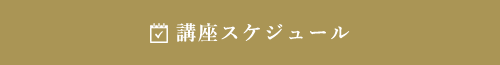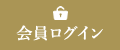- ホーム
- 資産運用、NISAと保険どっちが賢い??
資産運用、NISAと保険どっちが賢い??
変額保険とNISA、資産運用における本当の役割とは?
本質的な資産形成を考える上で押さえておくべき比較視点
金融業界の中でも、特に、ファイナンシャルプランナー(FP)や保険営業マンとして活動されている皆さんは、ここ数年、お客様と向き合う現場で「NISAってどうなんですか?始めた方がいいんですか?」という質問を受ける機会が増えてきていることかと思います。
これまで「資産運用といえば変額保険」と自信を持って提案してきた方にとっては、少し戸惑いや迷いを感じる瞬間かもしれません。事実、金融庁が推進するNISAは非課税枠が恒久化され、一般家庭でも“使わないと損”と言えるほど大きなメリットのある制度として推進されています。
ここでは、お客様に最適かつ本質的な資産形成策をお届けするために、変額保険、NISAそれぞれがどの様な特徴や価値をもっているものなのかを改めて見つめ直し、金融業界に身を置く皆さんと共に、両者の特徴を整理して理解し、今後のお客様への提供価値について考えていきたいと思います。
1. 変額保険の特徴と強み
(1)変額保険とは
周知のとおり、変額保険は、支払った保険料の一部を特別勘定で運用し、その成果によって保障額や解約返戻金、年金原資が変動する商品です。保障と資産形成を同時に実現できる点が大きな特徴と言えます。
(2)メリット
• 死亡保障と資産運用の両立
万一の際には死亡保険金が支払われるため、「保障を確保しつつ運用したい」というニーズに応えられます。
• 保険料払込免除特約が使える
三大疾病や上皮内がんと診断されると以降の保険料支払いが免除され、それでも保障と運用は継続します。これはNISAや投資信託にはない安心感です。
• 強制貯蓄の仕組み
契約を継続しやすいため、積立投資を「続ける仕組み」として機能します。
• 税制メリット(解約時)
解約返戻金を受け取る際、所得区分が「一時所得」となり、最大50万円の特別控除や課税計算の軽減措置を受けられる場合があります。これにより投資信託をNISA口座ではなく、証券会社の一般口座や特定口座で運用した場合にかかる「運用益×20.315%」の税負担を抑えやすいのが実際の強みです。
• 相続・贈与対策に有効
最後に、変額保険に限ったことではなく、生命保険共通のメリットになりますが、死亡保険金は「みなし相続財産」として500万円×法定相続人の非課税枠を利用可能。資産移転のニーズにも対応できます。
(3)デメリット
• コストが高い
保障コストや運用管理費が差し引かれるため、同じファンドを直接買った場合よりリターンは低くなりがち。
• 流動性が低い
特に契約初期は解約返戻金が少なく、短期解約は大幅な元本割れにつながるリスクあり。
• 投資先が限定的
保険会社が選定した特別勘定の範囲でしか運用できず、証券口座と比較し、自由度に劣る。
2. NISA(投資信託)の特徴と拡大する存在感
(1)NISAとは
NISAは、投資による利益や分配金が非課税になる制度です。2024年から現行のNISAが始まり、非課税枠が恒久化、年間360万円、最大1,800万円の非課税投資が可能になりました。
(2)メリット
• 運用益が非課税
前述の通り、通常、証券会社の一般口座や特定口座で運用した場合には、運用益に対して20.315%課税される利益が非課税になり、長期運用の複利効果が最大化されます。
• 低コスト運用が可能
信託報酬0.1%前後のファンドなども存在し、運用の効率性では変額保険を上回ります。
• 流動性の高さ
必要に応じていつでも売却可能。住宅資金や教育費など、ライフイベントに柔軟に対応できます。
(3)デメリット
• 保障は一切ない
死亡保障や疾病保障、保険料払込免除などの保障はなく、あくまで投資商品。万が一に備える場合には、別途保険加入の検討が必要です。
• 自己管理が必要
投資信託の選定や継続は顧客自身に委ねられるため、金融リテラシーに不安のある方の場合は、本質的な資産運用についてのレクチャーなどを合わせて行った上で、顧客が納得の上で、自身の判断で投資・運用を指図していく必要があります。
• 未成年向けNISAは存在しない
2024年以降、未成年向けのジュニアNISA口座は廃止されているため、子どもの名義で資産形成をする場合は通常の課税口座で「未成年口座」を開設し、運用せざるを得ません。(将来的には未成年向けに制度が改訂される可能性もあります)
3. 子ども名義での資産形成を考えるなら
ここで意外と見落とされがちなのが「子ども名義の資産形成」です。
現状、未成年にはNISAが使えません。そのため、教育資金などを子どもの名義で資産形成したい場合、証券口座での投資信託購入は課税対象になってしまいます。
一方で、たとえば年金型の変額保険などは、保険商品であるものの「保障」は極力小さく、保険料の大部分が運用に回り、投資信託と遜色のない運用効率を実現できる商品も存在しています。子ども名義で加入することができ、解約時の税制は前述の「一時所得扱い」となり、保険商品ならではの課税メリットが受けられます。つまり、
• 子どもの名義で積立可能
• 保険商品だが「保障」極力小さく、運用も投資信託とほぼ同様に効率的。
• 解約時の課税負担を軽減できる
といった理由から、NISAが使えない子ども名義の資産形成では「変額保険の活用も合理的」と考えることもできます。
4. 両者をどう整理して提案するか
ここまでの比較をまとめると、
| 変額保険 | NISA(投資信託) | |
| 目的 | 保障+資産形成 | 純粋な資産形成 |
| 税制メリット | 生命保険料控除、一時所得控除、相続税非課税枠 | 運用益非課税 |
| 払込免除特約 | あり(疾病時も保障・運用継続) | なし |
| コスト | 高い(保障コストなど含む) | 低コスト商品多数 |
| 流動性 | 低い | 高い |
| 運用の継続力 | 高い | 低い |
| 子ども名義 | 可能(例:変額年金保険など) | 不可(未成年NISA廃止、18歳以上可) |
| 保障 | 死亡保障あり | なし |
両者を同じ土俵で「どちらが良いか」で語るのではなく、役割の違いを理解したうえでハイブリッドに提案するのが賢明です。
5. 今後の提案スタイル
営業現場で信頼を勝ち取るには、「保険しか知らない」から脱却し、「NISAも含めた資産形成の全体像を語れる金融のプロ」になることが求められています。
• 基本的な資産形成はNISAで非課税・低コスト運用
• 保障や疾病リスク対応は保険(変額保険含む)
• 子ども名義の運用や相続対策では変額保険を活用
こうした提案は「NISA vs 変額保険」という対立を超え、お客様にとって本当に最適な選択肢を提示できます。
まとめ
• 変額保険は「保障+資産形成」の両立に加え、払込免除特約や解約時の課税メリット、子ども名義での活用など独自の強みがある。
• NISAは「非課税+低コスト」で純粋な資産形成に優れるが、保障や未成年口座では弱点がある。
• 営業マンに求められるのは、両者を正しく理解し、お客様のライフプランに応じて最適な組み合わせを提案する姿勢である。
ここまで見てきたように、「資産運用=変額保険」と一律に考える時代は終わりました。これからは「NISAも変額保険も、双方を深く理解しているからこその最適提案」が、顧客からの信頼を獲得できる「金融のプロ」としての最低条件になる、と言っても過言ではありません。
また、両者に共通するのは「投資信託」を用いた運用。保険営業の現場では、あまり根拠を持たず、理解が深まっていない状態で特定のファンド(特別勘定)を「人気」「パフォーマンスが良い」とご提案するシーンも多く見受けられるのが現実です。しかし、本来は、金融のプロとして本質的な資産形成を深く理解し、ファンド(特別勘定)についても根拠を持った説明を通じ、お客様自身が納得の上で選択し、運用をスタートすることがとても重要と言えます。「保険しか知らない」から脱却し、資産形成への深い理解を踏まえた最適なアドバイスができる「金融のプロフェッショナル」へ。
金融教育学会では、その一歩を踏み出すための深い学びを提供しています。ぜひ、共に一段階上のステージに向けて、学びをスタートしましょう!
【金融教育】金融リテラシー・資産運用に関するコラム
- 【金融の学校】資産形成の基礎から学べるプロのための講座について
- 【金融の学校】金融教育インストラクターの資格とは?講座に参加して知識・スキルを強化
- 【金融リテラシーとは】学校の金融教育必修化はプロにも影響!プロ向け講座に参加を
- 教育現場で金融教育が必修化!求められる高度な金融リテラシーとは
- 金融教育の先生として求められる金融のプロ!資格を取得して顧客・社会に貢献
- 資格を取得して金融リテラシーを向上!高度な金融教育が行える人材を育成
- 資産運用のプロとしてぶれないアドバイスを!資格取得を目指そう
- 金融のプロのための講座で資産運用アドバイススキルを向上!
- 【本質的な金融教育】資産形成のアドバイススキルを習得!プレセミナーに参加を
- プロ向けの資産形成教育とは?金融のプロが学び続けなければいけない理由
- 資産運用、NISAと保険どっちが賢い??
資産形成を学ぶプロ向け教育なら上地ゼミ金融教育学会
| 運営会社 | 合同会社FITアソシエイツ |
|---|---|
| 組織名 | 上地ゼミ金融教育学会 |
| 所在地 | 〒278-0022 千葉県野田市山崎1564番地の21 |
| TEL | 080-1104-8911 |
| メール | info@fit-edu2020.com |
| 事業内容 | 資格講座の企画・運営、金融教育コンテンツの作成、ホームページ・ゲーム・アプリの企画・運営 |
| URL | https://fit-edu2020.com |